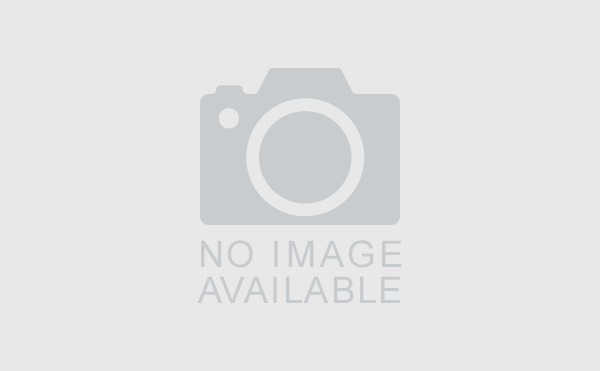新年度によせて
ご入学、ご進級の皆様、おめでとうございます。
ご指導者様、保護者様におかれましても、
気分も新たにお過ごしのことと存じます。
何かと慌ただしい新生活の4月。
ちょっとした空き時間に、モチベーションの向上に、
パンセでは3段階の実力判定問題を公開中です。
今回は第2弾、一般入試レベルです。
せっかくこのページを訪れて下さったあなたに、
入試楽典のポイントをこっそりお教えしましょう。
一、出題パターンに慣れる
楽典問題は、設問文の言い回しが独特です。
また短調の種類と扱いや、楽典上の異名同音調など
明文化されない前提も多いのです。
たとえ音楽の知識があっても、
「何を聞かれているかわからない」と、
得点することができません。
しかし、知っていれば解けるのですから、
数多くの出題パターンを体験しておけば安心です。
二、数字の扱いに慣れる
調性音楽では、同じ音でも背景の調によって、働きが変わります。
そのためドレミなどの音名ではなく、数字の使い分けによって、
音楽の様々な概念と音組織を説明していきます。
楽典が苦手な人は、アラビア数字・漢数字・ローマ数字の使い分けを見て
「それが何を指しているのか?」を整理・復習すると、点数が伸びますよ。
三、多項目にまたがる問題に慣れる
楽典のテキストでは、音程→音階→和音…と単元ごとに順序良く学びますが、
実際の入試では、例えば「○○音を××度とする□□調の〜」というように、
一見すると音階問題でも、実は和音や調関係を組み合わせた問題になっています。
この意識が抜けていると、永遠に解けずに苦しむことになります。
(しかし、もちろんこれらを効率良く解く方法が
ありますから、 ご心配なく!)
四、最後に
会員の皆様には既にお伝えした通り、楽典と聴音は春夏が勝負!
是非下記の問題を活用し、合格へ向けて第一歩を踏み出してください。
教材選びや学習計画に迷ったら、お気軽にお電話ください。
経験豊富なスタッフが、親切にお答えしています。
共に頑張っていきましょう!
Tel free 0800-1234-500
教材をお探しの方は こちら